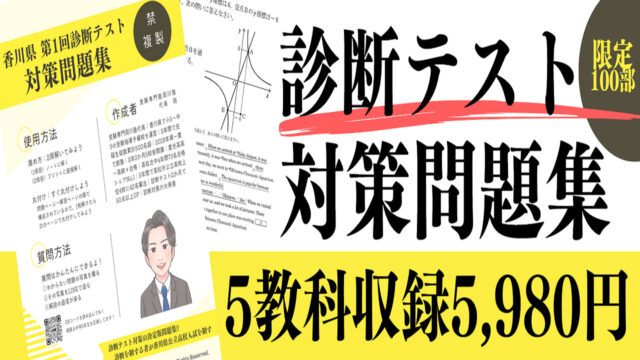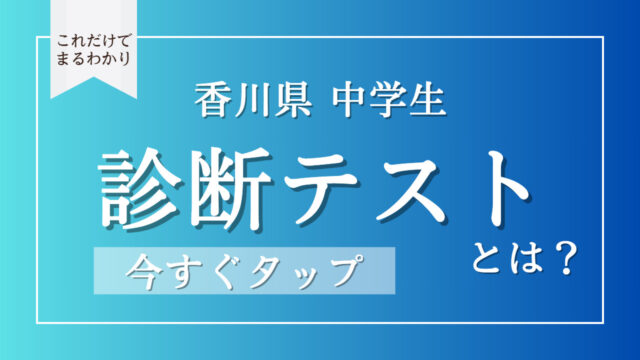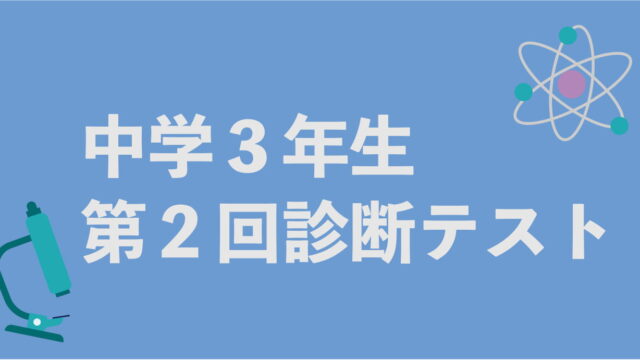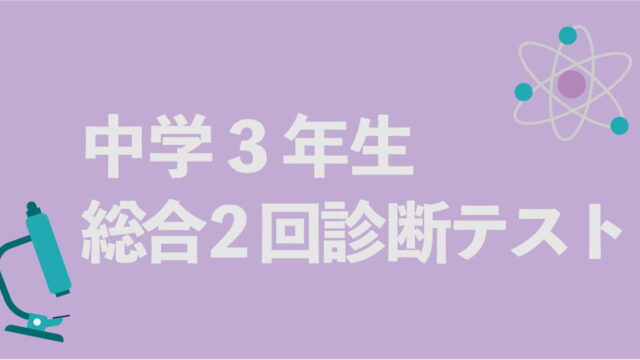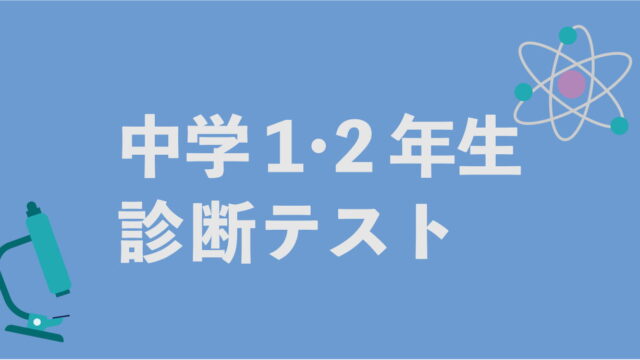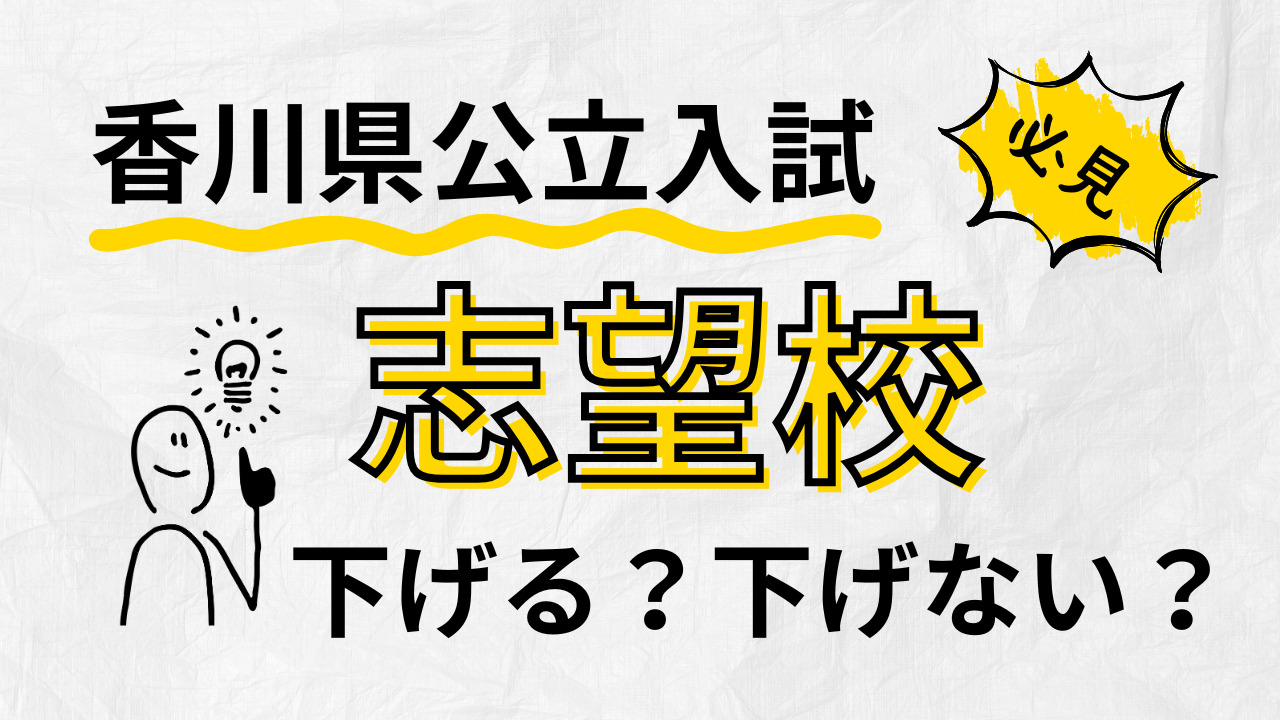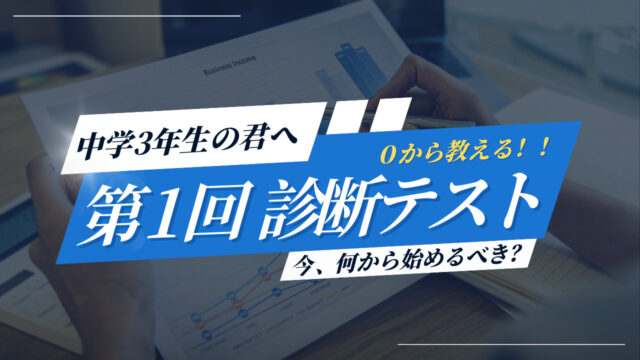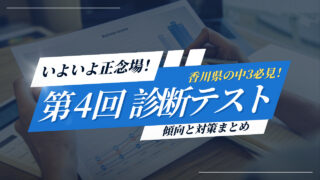公立高校入試における志望校の選定は、受験生にとって極めて重要な意思決定です。
中でも「志望校を下げるべきかどうか」は、多くの家庭や生徒が直面する悩みの一つです。
直近の第2回診断テストや現状の内申点から、まさに今、志望校を下げることを検討している中学3年生もいるのではないでしょうか?
ただし、志望校を早い段階で下げるという判断は、必ずしも最善とは限りません。
タイミングと判断の根拠が極めて重要です。
志望校を早期に下げるリスク
志望校を検討する過程で、「安全志向」に傾きすぎて、まだ実力が伸びる可能性がある段階で目標を下方修正してしまう受験生がいます。
しかし、志望校を早くから下げると、明確な目標がなくなり、モチベーションの低下につながる可能性があります。
事実、多くの指導現場で見られるのは、志望校を高く設定していた生徒の方が、その目標を維持することで学習に集中し、結果的に成績が伸びやすいという傾向です。
反対に、
「どうせ無理だろう」
「安全に行こう」
と早々にランクを下げた場合、その時点から努力の意欲が薄れ、成績が横ばい、もしくは下降してしまうケースも少なくありません。
したがって、現実的なリスク管理は必要であるものの、「下げる」という選択は、成績の推移や本人の成長余地を十分に見極めた上で行うべきです。
判断すべきタイミングと基準
志望校を見直す最も現実的なタイミングは、冬の三者面談(11月〜12月)以降です。この時期には、内申点が確定し、診断テストの結果も出揃ってくるため、データに基づいた進路判断が可能になります。
以下のような場合には、志望校の見直しを真剣に検討すべきです。
-
内申点が志望校の基準に届かず、大幅な差がある
-
本人の学習意欲が著しく低下しており、改善の見込みが薄い
-
私立併願校の確保が難しく、公立一本に絞らざるを得ない状況
ただし、これらの条件に当てはまったとしても、「可能性がゼロではない」のであれば、本人の意志や努力次第で挽回の余地はあります。
ここで重要なのは、成績の伸びしろと、残された期間内での現実的な成長予測を冷静に判断することです。
「志望校を下げる=諦め」ではない
志望校を見直すことは、「目標を諦める」というネガティブな行為ではなく、「戦略的な選択」です。
第一志望へのこだわりも重要ですが、それ以上に大切なのは、自分の実力と環境に見合った進路で、安定して学び、成長できるかどうかです。
また、「安全校に入って上位を狙う」「高校でリベンジして大学受験で巻き返す」など、進路は一度きりではありません。
高校入試は人生の通過点であり、将来を見据えた柔軟な選択が求められます。
まとめ:下げる判断は「直前期」に。早期の見切りは避ける
志望校を下げるかどうかの判断は、本人の努力の成果がある程度見え始める直前期(1月〜2月)が最適です。早い段階で諦めムードになると、成績低下を招くリスクがあるため、「最後までチャレンジする意志」を持ち続けることが大切です。
目標を高く持ち、努力を継続した上で、最終的に現実的な判断をする。この姿勢が、後悔のない進路選択につながるのです。